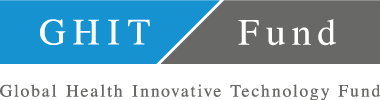STAKEHOLDER INTERVIEWS
グローバルヘルスR&Dに関わる
ステークホルダーへのインタビュー
この5年で日本が変わったこと
今後日本と世界が進む未来
DISCOVERY
03
北 潔
東京大学名誉教授
長崎大学大学院 熱帯医学・
グローバルヘルス研究科 教授・研究科長
“NTDsは、患者のクオリティー・オブ・ライフだけでなく、経済的な発展、子どもの成長、国の成長や発展に必要な要素をどんどん奪っていくということを、身をもって痛感しました。”
北教授が、寄生虫、感染症の領域をライフワークにされた経緯について教えてください。
もともと私は、大学院までは完全に純粋な生化学の研究をやっていました。大腸菌を使った、エネルギー代謝に関する新たな発見をして、それで博士の学位を取ったのですが、同じような仕組みがもう少し高等な生物にもあるのではないかと思って、最終的に行き着いたのが寄生虫の分野でした。
その後、東大の理学部で助手をしていたのですが、1983年に順天堂の寄生虫学教室に入れていただいて、寄生虫を中心に基礎研究をやろうと考えていました。ところが、ちょうど1年半ぐらいしたところで、国際協力機構(JICA)の医療協力プロジェクトのチームリーダーとして、パラグアイに行くことが決まりました。1984年から約1年半、パラグアイでシャーガス病やリーシュマニアの患者さんの流行調査などを行っていました。フィールド調査に行く前に、村長さんと事前に打ち合わせをするのですが、「血液検査で陽性が出たときはどうするのですか?」と聞かれて困ったのを覚えています。なぜかと言うと、薬がないわけではないのですが、副作用が強い薬しかなかったのです。それからもう30年近く経ちますが、それ以降も新しい薬はほとんど出てきていません。
こういう病気が厄介なのは、致死的ではないため、つい研究が後回しになってしまいます。顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases: NTDs)は大体そうですけれども、マラリアみたいに放っておくとすぐ亡くなってしまうというような致死的な病気の場合には、比較的研究費が付きやすく研究も進みます。しかし、特にシャーガス病やリーシュマニア症などは徐々に症状が進んでいきます。こうした病気は、患者のクオリティー・オブ・ライフだけでなく、経済的な発展、子どもの成長、国の成長や発展に必要な要素をどんどん奪っていくということを、身をもって痛感しました。
その後、日本に帰ってきてから、こうした病気は日本にないけれども、薬やワクチンを開発するために基礎研究と応用研究を両輪にして、特に感染症の中でも寄生虫の創薬をやろうと考え始めました。それから10年以上経って、世界のグローバル化とともに、グローバルヘルスという概念が徐々に浸透し始め、この寄生虫の分野は非常にダイナミックになってきました。自分が大学院を出たころは、まさかこういう仕事をやることになるとは夢にも思っていなかったのですが、そういう自分の基本的な興味が何か役に立つところにつながるというのは、非常にやりがいがあることだと思っています。
“寄生虫病や感染症を撲滅するには、良い薬やワクチンを作るための研究開発と、公衆衛生の2つのアプローチの両方が必要不可欠だと思っています。”

日本における感染症の歴史について教えてください。
ここ長崎は港町ということもあって、外国の船が運んできた病気などが結構あったわけです。昔から感染症というのは、日本だけでなく世界中どこでもあったわけですが、日本は島国ということもあり、比較的ある程度守られていたのだと思います。ただ、外国の船が着いたおかげで、例えば下痢症が港町に広がったりするという事例も起こっています。九州全体で言えば、熱帯に比較的近く、気温が高いということで様々な病原体も増殖しやすく、特に蚊などの病原体を運ぶベクターの生息の条件にも合っています。やはり温暖な地域から熱帯地域にかけては、感染症が流行しやすい。そのため、現在の長崎大学熱帯学研究所の前身となる風土病研究所が、こうした感染症の研究や対策に大きな役割を果たしてきました。
現代になるにつれて、徐々に日本の感染症研究が発達してきて、ご存じのように例えば志賀潔先生が赤痢菌を見つけたりですとか、それから寄生虫の分野でいうと、宮入慶之助先生が日本住血吸虫の感染を媒介する中間宿主のミヤイリガイを見つけて、日本住血吸虫の感染経路を解明する突破口となりました。こうした科学的な発見が、病気を防ぐための対策、つまり公衆衛生的な対策につながっていったのです。住血吸虫症の場合は、ミヤイリガイを殺貝するために、田んぼのあぜ道を全部コンクリート化したり、患者さんがいたら、プラジカンテルという薬で治すといったことを徹底的に行われました。1978年の山梨での感染例を最後に、日本では住血吸虫症を完全に根絶することができました。
また別の話としては、西郷隆盛は晩年、フィラリア症で陰嚢水腫になっていたことも有名です。馬にまたがって乗れなかったのです。ですから、西南戦争の最後には、かごに乗って鹿児島へ戻ってきたという逸話があります。実は、九州や四国、沖縄などではフィラリアが大きな問題になっていました。フィラリアの場合、夜中にミクロフィラリアという原虫が血液中に出てくるので、夜中に住民に公民館に集まってもらって、一人ひとりきっちりと採血をして、それで感染していると判明すると、すぐジエチルカルバマジンという薬で治す。このように、丁寧に診断と治療を行うことが非常に重要だったわけです。それから、沖縄などでは雨水をためた天水を使うことが多く、そういった所にボウフラがわくため、蚊が繁殖する温床になっていました。フィラリアを媒介するのは蚊なので、そのための蚊対策も必要でした。
他には、特に戦後、95%以上の人が回虫に感染していた時期があって、これも官民学が一体となって、徹底的に駆虫したおかげで、今では回虫の感染率は0.1%以下になりました。
先の風土病研究所の先生たちや、地方の保健所、衛生研究所、そして住民が一体となって、地道に、徹底的に感染症を一つ一つ潰していったわけです。これはやはり日本の国の公衆衛生の仕組みと、寄生虫の基礎・臨床研究がうまくかみ合った成功事例だと思います。そのおかげで日本からは、マラリア、住血吸虫症、フィラリアなどの寄生虫病は撲滅されました。これらの日本の経験は、その後、官民学の取組みを通じて、世界各国に日本のノウハウが提供されていきました。必ずしも日本の経験がそのまま開発途上国で使えるわけではないので、その国の実情や環境にあった形で改善、応用していく必要性がありました。今後もこうした寄生虫病や感染症を撲滅するには、良い薬やワクチンを作るための研究開発と、公衆衛生の2つのアプローチの両方が必要不可欠だと思っています。
“日本と海外の研究グループがパートナーシップを組んでプロポーザルを書き、製品開発を進めるというのは、日本のアカデミアの本当のグローバル化、研究を骨太にするという意味で非常に意義深いと思います。”
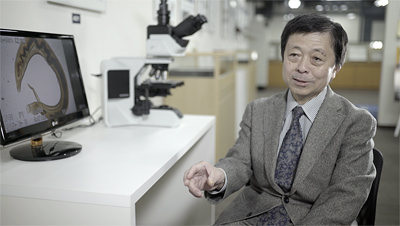
日本のアカデミアの強みは何でしょうか?
科学がいろいろな分野で発展してくる中で、日本の強みは、1つはこつこつとやるところだと思います。地道ではあるけれども、頭を使って、戦略を立てて基礎研究をしっかりやることです。もう1つは、例えば、日本にはSPring-8という非常にすぐれた施設があり、最先端科学を用いて、コンピューターを用いた優れたドラッグデザインを行うこともできます。寄生虫のような日本にもう存在しなくなってきている病気を、日本にある最先端の科学技術を使って研究できるということは大きな強みだと思います。
ノーベル賞を受賞された大隅良典先生が、光学電子顕微鏡で酵母を観察し続けた末に発見したオートファジーなどがその良い例です。私は、大隅先生と同じラボに6年間一緒にいたのですが、基礎研究の重要さを常におっしゃっていました。当時、私らがいたのは東大の理学部だったのですが、大隅先生とディスカッションをしていて、「それは役に立つね」と私が言うと、「君の科学は二流だね」と冗談半分に言われました。北里大学の大村智先生もそうですが、基礎研究を丁寧に行うことが、ひいては最終的に世の中の役にたつと私は信じています。例えば、マラリア原虫の生物としての特性を、基礎研究を通じて詳細に理解しておけば、マラリアの薬剤耐性が起きたときにも対応策を考えることができるのです。それを一足飛びにやってしまうと、どう対処していいかわからなくなるかもしれません。
日本は、今すぐには役に立たない研究でもしっかりと支援しようという雰囲気が最近また盛り上がってきた感じがしています。ですので、近視眼的ではないアプローチも非常に重要だし、今後もその点を大事にし続けて欲しいと思います。
現役の研究者であり、GHIT Fundの選考委員長であるということ
GHITが設立されるという話をうわさで聞いていたので、自分の研究をGHITに応募したいと思っていました。私も現役研究者ですので、こうした研究費が得られる機会は研究者にとってはありがたいものです。その後、厚生労働省と外務省の方が私の所に来られて、選考委員長になってくれないかというお話しを頂きました。基金としての規模も大きいし、逆にこれをいいかげんな人が選考委員になってやったら、納税者である日本国民にとっても良くないなと思いました。GHITの設立時点では、研究する側ではなく、選考する側として何らかの貢献ができるのであればそちらの方に専念しようということで、選考委員長をお引き受けしました。
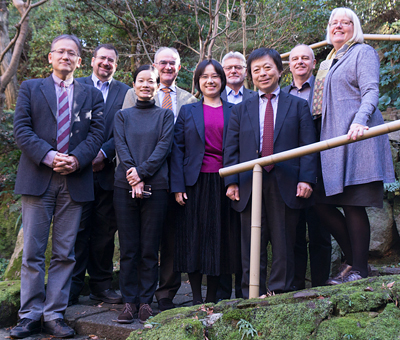
国際的なメンバーで構成される選考委員会をどうリードしているのでしょうか?
私自身はイニシアチブを取って、ディスカッションをまとめあげたり、自分の意見を強く主張するというよりは、日本人以外の選考委員に、日本の環境や背景情報を適切に、正しく伝えることに主眼をおいています。海外の選考委員は、日本の事情を知らない場合があるからです。例えば、この研究者は基礎研究の部分では非常にいい仕事をしているとか、この日本企業は、海外ではあまり知られていないけど伝統的に抗生物質を開発してきた企業なんだとかいうことをちゃんと伝える。GHITでは、プロポーザルの評価・審査に関して、外部審査員と選考委員による二段階評価を行った後に、応募者と選考委員とのインタビューを行うというように、複数の過程を踏んでいますので、選考の方向性は自ずと見えてきます。したがって、私が選考委員長としての役割は、日本の現状を正しく伝え、反映することだと考えています。
GHITの評価システムの特徴とは?
繰り返しになりますが、GHITの選考委員会がプロポーザルを評価・審査する前に、国内外の外部審査員が先にプロポーザルを評価する仕組み(以後、評価システム)は、非常に良いやり方だと思っています。外部審査員の先生方にとっては大変な労力だと思いますが、プロポーザルをしっかりと読み込み、コメントもぎっしりと書いてくれています。選考委員は、もちろん自分たちでも客観的にプロポーザルを評価しますが、外部審査員の多様かつ専門的な意見を参考にすることができるので、非常に助かっています。
このような評価システムは科研費等でも導入されていますが、1段階と2段階の評価のギャップが大きい場合があります。審査員の専門性がプロポーザルの内容と合致していないことで、正しくない評価や判断が紛れてしまうことがあります。一方、今のGHITの評価システムですと、仮に専門ではない外部審査員がプロポーザルを評価してしまい、的を外したコメントした場合があっても、一つのプロポーザルにつき外部審査員3名がそれぞれ独立して評価を行っているので、最終的に評価の質は担保される仕組みになっています。そういった意味で、理想的だと考えています。
そして、外部審査員と選考委員から高い評価を得られた案件については、その後、選考委員会とのインタビューが設けられているので、フェアで、しかもいい案件を選定できるシステムになっていると思います。
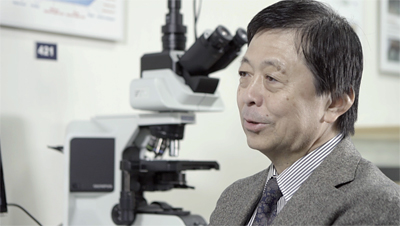

選考委員会での応募者とのインタビューについてはどう思われますか?
選考委員会とのインタビューに呼ばれた場合、日本人の方が研究代表者の場合で、欧米で経験を積まれた日本人研究者なら問題ないかと思いますが、インタビューの経験がないと、プレゼンはできますが、質疑応答のところでどうしてもネックになります。選考委員からの質問の意味が正確に伝わらないとか、逆に、伝えたいことが選考委員に伝わらないということもあります。ただ、科学は英語でやるしかないので、日本もそういったレベルでやらないといけない時代です。
例えば、学会であれば、自分の研究結果を発表して、それを専門家同士でディスカッションすればいいのですが、GHITの場合はそもそも治療薬やワクチンの製品開発です。専門領域以外の人たちにも、「この研究が治療薬やワクチンになるんだ」ということを科学的に説明するだけでなく、製品化に向けた道筋も明確に示さなければなりません。これは、正直、日本のアカデミアにはハードルが高いものだと思います。そういう意味でも、日本と海外の研究グループがパートナーシップを組んでプロポーザルを書き、製品開発を進めるというのは、日本のアカデミアの本当のグローバル化、研究を骨太にするという意味で非常に意義深いと思います。現状としては、まだレベルが追い付いていないところもありますが、もう少し時間が経てば、この敷居の高さというものはなくなるだろうなと思います。
マイルストーン&ステージゲートを用いたプロジェクトの進捗評価はどう思いますか?
最近、日本の他の団体でも行われるようになってきたと感じるのですが、おそらくこのきっかけになったのは、GHITの評価システムが影響していると思います。そういった意味で、多くの人たちがGHITに応募しているので、それが他の団体にも波及しているのかなと思います。GHITが導入した、日本と海外のパートナーシップを必須条件にするとか、評価システムそれ自体が、国内の機関にもかなり影響を与えていると感じます。今、いくつかの案件が臨床試験に進んでいますから、今後さらに具体的な成果が現れているのではないかと期待しています。もし、そこで開発スピードがあまり上がらないという場合には、今の進捗評価の仕組みを考え直す必要があるかもしれませんが。
今のGHITの進捗は、開発のスピードがダウンしていないし、これは最初の選考過程できちんとした選考を行っていたということだろうと思います。それから、GHITの皆さんがその後のフォローをきちんとして下さっているということなのだろうなと思っています。ですから、今後の私の願いとしては、GHITのプロジェクトの中から、感染症の流行地で実際に患者さんに提供できる製品が出て来ることです。10も20も製品化されるとは思いませんが、やはり重要な病気に関しては、早く製品が出ることを期待しています。
日本のこの4年間での変化は?
GHITの設立当初は、当然ながらGHITのことを知らない人も多かったと思いますが、徐々に日本でも知れ渡ってきたと思います。そして、今では、基礎研究や合成研究をやっているグループの中には、例えば安全性試験までいったら、「目指せGHIT!」などと言って、GHITに応募しようと頑張っているところもあります。こういった姿勢もこれまでの4年間でアカデミアが変わってきたところだと思います。
先ほども申し上げましたが、基礎研究自体は英語で論文を書いて、ピアレビューの国際的な学術誌に出さないと評価されませんから、その点に関しては以前から皆やっていました。しかし、実際に研究成果を生かして海外のグループと一緒に製品開発を行うということは稀なケースでした。しかし、特にこの感染症の分野では、いいシーズや研究テーマがあってグローバルなパートナーシップが組めれば、GHITなどのような団体から資金を得られる機会が増えてきました。ですから、研究者の頭の中が、国内からグローバルなほうに急激にシフトしつつあるわけです。
自分もそうですけど、日本人はあまり自分からアピールするというのは得意ではないし、あまりそういう差し出がましいのは美しくないと考えてしまう傾向があります。でもせっかくGHITのような仕組みがあって、極めてユニークな取り組みなので、これをさらに国内外に向けて発信し続けることが大切だと思います。GHITを活用することが、日本のアカデミアのさらなる成長・発展のためには良いことだと思います。
“私が寄生虫学を研究するのは、チャレンジングな領域であり、応用可能性もあって、グローバルヘルスにも貢献できる、一石三鳥の分野だからだと思います。これが私のモチベーションです。”
基礎研究において、第二期においてGHITに期待することは何でしょうか?
私の主観的な印象ですが、GHITの設立当初は、やはり、良いプロポーザルが最初出て来るのは当然だと思うのですが、例えば海外で開発して止まっていた案件で、日本の企業と組んだことで開発が動き出したというものがあります。それはそれでうまくいっているものがあります。最初は、みんな出口に比較的近い案件が多かったと思いますし、もちろん今でも出口が近いもので、本当に良いものはどんどん取り上げていく必要があると思っています。
その一方で、最近では、探索研究や基礎研究などにも目を向けるようになってきています。遠い将来を考えれば、後ろに続いているものがないと、臨床試験など後期案件が失敗した時、急に何もなくなってしまいます。そういう点で、最近のプロポーザルというのは早期段階のものも出てきていて、個人的には、将来を考える上では非常に良い方向性だと思います。 最後に、今、私の周りには、GHITに応募している研究者が多くいます。その中から最終的に投資を受ける案件が出てきて、良い研究を進めているのを見ると嬉しく思います。また、選考に落ちたとしても、なぜだめだったかを改めて検証して、ぜひ再度トライして欲しいと願っています。
最後に、北教授の研究に対する情熱はどこから来るのでしょうか?
私は、世界中色々な国に行く機会がありますが、生まれた国によって子どもたちの一生が左右されてしまうというのは非常に理不尽だと思っています。生まれてきた子どもたちがすくすくと育って、そして世の中の役に立って、そして天寿を全うする。これを実現するために、特に感染症の分野で、自分は何をしたらいいかとずっと考えてきました。
日本だと寄生虫の患者さんは少ないですが、グローバルに見たら寄生虫の患者さんというのは非常に多い。感染症の中でも、ウイルスや細菌は研究者もたくさんいますが、そういう意味では少なくとも寄生虫学者は多くはない。寄生虫は真核生物なので、いわゆる抗生物質も効かないしワクチンもない。ですから一番チャレンジングな病原体だと思うのですね。だから相手にとって不足ではないし、研究のやりがいがあるのです。
さらに、寄生虫は「がん」と似ているところがあって、寄生虫のために開発した薬が、ある種のがん細胞の増殖をぴたりと止めることもある。つまり、他の研究分野にも応用できる可能性が高いと思っています。
私が寄生虫学を研究するのは、チャレンジングな領域であり、応用可能性もあって、グローバルヘルスにも貢献できる、一石三鳥の分野だからだと思います。これが私のモチベーションです。
本インタビューに掲載の所属・役職名は、2017年のインタビュー公開時のものです。
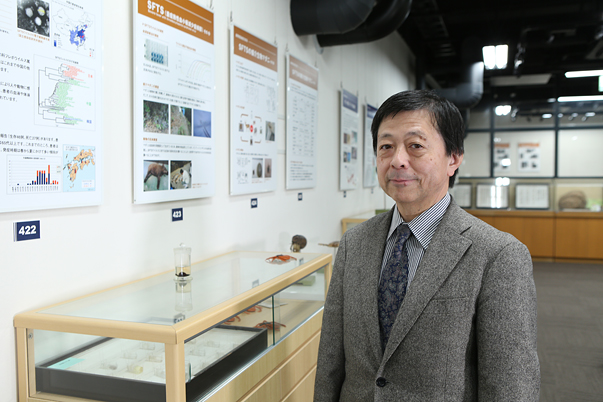
- 略歴
- 北 潔
東京大学名誉教授
長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 教授・研究科長
昭和49年東京大学薬学部卒業、同研究科博士課程修了。東京大学理学部助手、順天堂大学医学部助手、講師を経て、平成3年より東京大学医科学研究所助教授、平成10年より東京大学大学院医学系研究科教授。平成27年より現職。日本寄生虫学会理事長、専門は生化学、寄生虫学。
STAKEHOLDER INTERVIEWSARCHIVES
FUNDING
-

01
山本 尚子厚生労働省 大臣官房総括審議官
(国際保健担当)
#
-

02
ハナ・ケトラービル&メリンダ・ゲイツ財団
グローバルヘルス部門ライフサイエンスパートナーシップ
シニア・プログラム・オフィサー
#
-

03
スティーブン・キャディックウェルカム・トラスト
イノベーションディレクター
#
DISCOVERY
-

01
デイヴィッド・レディーMedicines for Malaria Venture (MMV) CEO
#
-

02
中山 讓治第一三共株式会社
代表取締役会長兼CEO
#
-
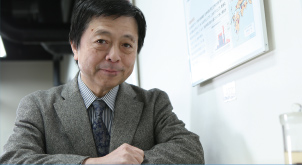
03
北 潔東京大学名誉教授
長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス研究科 教授・研究科長
#
DEVELOPMENT
-

01
クリストフ・ウェバー武田薬品工業株式会社
代表取締役社長 CEO
#
-

02
畑中 好彦アステラス製薬株式会社
代表取締役社長CEO
#
-

03
ナタリー・ストラブウォルガフト顧みられない病気の新薬開発イニシアティブ(DNDi)
メディカル・ディレクター
#
ACCESS
-

01
ジャヤスリー・アイヤー医薬品アクセス財団
エグゼクティブ・ディレクター
#
-

02
近藤 哲生国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所
駐日代表
#
-

03
矢島 綾世界保健機関西太平洋地域事務所
顧みられない熱帯病 専門官
#